映画館で眠る少年は、なぜイサバのカッチャになったのか? その1 ~十日市秀悦さん
ささやかな反乱と高校演劇
祖父が今でいうスーパーマーケット、父が食堂を営む商売人一家に生まれた。「人が遊んでるとき稼がないで、いつまんま食うんだ」が口癖の両親には、子どもにかまっている時間はない。「そこで反乱起こすの」と十日市は笑う。
ささやかな反乱。それは近所の映画館に入り浸ること。今でこそ飲食店が立ち並ぶ長横町だが、当時は商店や住宅も多く、映画館も盛況だった。映画を観ながら眠り込んだところを、母が迎えに来る。
「守衛さんがもう電気消しちゃって。小さいから、後ろから見ると席に誰もいないと思って消すんでしょうね。それをおふくろが抱いて帰ってた。あれ、昨日映画館で寝たのに、なんで布団さ寝てらべって思った」 銀幕の住人―役者に憧れたのは、自然な流れだったのだろう。
一方で、なんとか両親を振り向かせる方法はないかと考えた。出した結論は「学芸会で主役やれば来てける(くれる)」
児童会長をしたり、校内弁論大会に出場したり、目立つことならとにかくやる。真面目一方というよりは、人を笑わせるのが好きな子どもだった。「裕次郎より由利徹(※①)」の言葉が、それを物語る。
また『笑わせる』ことは、十日市少年にとって、もっと深い意味も持っていた。
こんな話がある。当時、父と母はよくケンカをした。店の裏の二間だけの家で、深夜、怒鳴り合う声で子どもたちは目覚める。父がもう少しで母を叩くというところで、はね起きて襖を開け、『今日なさ、学校でこったら事あってさ(今日、学校でこんなことがあってね)、キンキンキラキラ』とおどけて見せると、両親は笑ってケンカをやめたものだ。「切ない話だけど、それが後を引いてる」
中学を卒業後、高校演劇界では全国的に有名だった八戸北高校へ進学。小寺隆韶(りゅうしょう)顧問のもとで厳しい練習に励む。東北で1校だけという狭き門を突破し、3年連続全国大会に出場。うち一度は日本一にも輝いた。
こうなると、役者になることはもはや淡い憧れではない。18歳の十日市少年は、期待に胸を膨らませて東京を目指した。
掃除係からスターの弟子に
演劇を専門的に学べる大学といえば、日本大学芸術学部。いわゆる『日芸』だ。
初日、教授が言った。
「将来役者になる奴は手を上げろ」 真正面の席を陣取った十日市は、はりきって挙手する。「何てばかな質問だ、当たり前だべって」 しかし後ろを振り返って愕然とした。29人のクラスメイトは、誰ひとり手を挙げていなかったのだ。

周囲は、モラトリアムを謳歌する付属高校出身者ばかり。少しずつ分かってきたのは、本気で夢を追っているのは自分だけらしいということ。
こんなはずではなかった…焦りを募らせながら月日は流れ、3年生の春。引っ越しをした。散歩をしていると、たどり着いたのは東映の撮影所。エキストラ募集の貼り紙を見たとき、これだ、と思った。
アパートから徒歩5分。終電車も関係ない。戦争映画の端役などで出演し、朝から晩まで夢中で過ごすうちに、俳優・梅宮辰夫の楽屋の掃除係に誘われた。
その頃の東映撮影所では、スターは撮影に来ても来なくても、常に楽屋が用意されていた。2階が鶴田浩二・高倉健・梅宮辰夫、1階に菅原文太、松方弘樹、千葉真一。それぞれに掃除係がつき、毎日掃除するということに表向きはなっていたが、実際には手を抜く者が多い。「隣の健さんの掃除係の人は、『来る3日前にやればいいんだ。もしかして3ヶ月撮影ないかもしれないんだぞ』って言いましたけど」
十日市は、来る日も来る日も一所懸命に掃除を続けた。
3ヶ月が過ぎたある日、階段を上ってくる耳慣れない靴音を聞いた。
「誰だべ」
扉を開けたのは『前略おふくろ様』の『秀次さん』。梅宮辰夫その人だった。
「『オレの部屋掃除してくれてんのはお前か』って、カッコいかったですね」
1週間の撮影の間、懸命に働いた。梅宮には既に付き人がいたが、最後の最後に言われた。「お前、オレんとこ来るか」
「田舎者の仕事ぶり見てらったんだね。バカ正直だから。それで助かったね、もし八戸でなかったら、手抜きを知ってる都会人だったらチャンスはないと思う。だから八戸に感謝しないとね」
こうして付き人生活が始まった。
兄弟子が去ったため、1ヶ月で必死に仕事を覚えた。たとえ深夜に帰宅しても、午前5時には起きる梅宮を、その日のスケジュールと移動の道順を頭に叩き込み、車を磨きあげて迎えにいかなくてはならない。
車は、3回切り返さないと曲がれないリンカーンコンチネンタル。弟子入りから1年間は「はい」と「いいえ」しか言うことができないほど神経を張り詰める日々。87キロあった体重は、半年で20キロ落ちた。
「苦しくてもなんでやめなかったんだべ、逃げださなかったべっていうと…。やっぱり夢あるすけ(あるから)だもんね」 梅宮のレギュラー番組があれば、12話完結のうち1~2回は出演できる。生活はギリギリ。けれど楽しかった。
「今までエキストラで、スターさんは遠い存在だったのが、このレベルの人達と同じ場所で仕事ができるんだもの」
既にお笑い界のスターだったビートたけしの弟子になる話もきたが、「私にとって師匠は親父さん一人です」と梅宮に啖呵を切った。
「かっこつけて。いつのまにか自分も東映になってたんですよ(笑) このとき行ってたら、たけし軍団6番弟子。一緒にフライデー襲撃してたね(笑)」
独り立ちのとき
気付けば4年の歳月が過ぎていた。
当時の芸能界には、2年以上付き人をすれば独り立ちは難しくなり、便利に使われるだけ、という定説があった。このままではいけないと考えた十日市は、付き人仲間と劇団を結成することを思いつく。『ピラニア軍団』(※②)にちなみ、その名も『付き人軍団』 由利徹やハナ肇、ショーケンこと萩原健一など、スターの付き人7~8人が、師匠のもとを辞して集まった。ところが、言いだしっぺの十日市だけは加わることができないでいた。後任が見つからなかったのだ。そんな状況で、梅宮に面と向かって「辞めさせてほしい」とはとても言えない。

そこで十日市は一計を案じた。
「私は幸せ者です。弟子になれて芸能界というものを一から教えてもらって、とても感謝しています。これまで道しるべを作ってもらったのは親父さんのおかげだ。だけどもやりたいことがある」
自分がどんなに忙しくても、十日市に仕事が入ると梅宮は決して「行くな」とは言わない。だから2ヶ月に及ぶ地方巡業の仕事を入れ、巡業先から、便箋20枚分の長い手紙を書いたのだった。
想いは通じ、いよいよ独り立ちの日がやってくる。
「秀、終わったか」
「はい」「お疲れ」
最後の日までいつもと同じ挨拶かと拍子抜けしていると、細長い箱を手渡された。
「開けてみろ」
出刃と刺身包丁の2本セットが光っていた。
「『秀』って入れといた」
「ハー、オラ別に、板場の修業に来たわけじゃない。実家はそうだけど…」
包丁は結局一度も使わずに、大切にしまってある。
「自分が包丁とか好きだから、オラのも作ったんでしょうね。不器用な人だから」
十日市は師匠をこう評する。
付き人軍団は、渋谷の小さなスタジオで旗揚げ公演を行った。内容は、舞台上に師匠の墓を立て、黒縁の写真を持って一人一人出て行き、「なんで死んだんですか」と勝手に殺して悪口を言うというもの。
「梅宮師匠、師匠は言ってたじゃないですか。コマーシャルは男は車か酒のしか出ちゃいけないって。なのになんで不二家パフィーのコマーシャル出てるんですか」
ギャグをまじえながら、師匠をこき下ろす芝居だった。最後にその写真を床に置いて〝踏み絵〟にし、『卒業おめでとう』と言って終わる。
過激なパフォーマンスはマスコミに歓迎された。怒る師匠は誰一人いなかったという。
「やっぱり、尽くしてもらったという気持ちがあったからでしょう。いいかげんにやってたら怒ったかもね」
自分だけのティッシュになれ
この公演は、十日市に転機をもたらす。たまたま公演を見に来た大手プロダクションにスカウトされたのだ。
当時、お笑いに力を入れ始めており、スター候補を集めているところだった。十日市は、そこで石塚英彦、恵俊彰と出会う。しばらくは男女混合のお笑い集団として公演を行っていたが、のちに、特に注目を集めた石塚、恵、そして十日市で『ホンジャマカ』を結成することになる。

そんなホンジャマカ結成の少し前。十日市は27歳にして、ゴールデンタイムの番組にレギュラー出演できるようになっていた。しかし、道は険しい。「プロデューサーが飲み会のとき、ニコニコ笑いながら肩たたいて『ギャラ泥棒』って。5000円しかもらってないのに(笑)」
番組は、新人お笑い芸人が成功者を講師に迎え、芸能界を渡って行くハウトゥーを教わるという趣向。芸人は最後の15分で講師に質問し、笑いを取らなければならない。30人中5人しかオンエアされず、オンエア率が低いと〝ギャラ泥棒〟 ダウンタウン、トミーズ、ダチョウ倶楽部など、そうそうたるメンバーがライバルだった。
それでも厳しい競争を勝ち抜き、ダウンタウンとともにトーク番組出演のチャンスを掴んだ十日市は〝言葉の壁〟に苦しめられる。
「大阪弁でまくしたてられたらね、難しい。今だったら八戸弁でやればよかったと思うけど、当時は標準語だったから、ワンテンポ遅いわけですよ。一瞬翻訳しちゃうんですね」
振られたネタを受けようとすると、横から瞬時に関西弁が飛ぶ。
「今だったら訳の分からない事を八戸弁でまくし立てるのに、分からなくても逆に面白くなるのに」
若き日の十日市には、その発想が持てなかった。ダウンタウンですら、楽屋では標準語を話していた時代。方言が新鮮で面白いと言われるようになるには、時機を待たなければならなかった。
一方、この頃にはメンバーも固まり、舞台を中心に活動していた『ホンジャマカ』も解散の危機を迎えていた。石塚が中ボケ、十日市が大ボケ、ツッコミは恵しかいない。舞台が失敗した後の気まずいムードが漂う楽屋で、恵が石塚と十日市、どちらと組むかの話になったとき、恵は十日市を指名した。のちのち分かったことだが、恵は、仲の良いダウンタウンの浜田に将来について相談しており、浜田は十日市と組むよう助言していた。
いわゆるピン芸人よりも、コンビのほうがやりやすい。誰も抜けたくなどないに決まっている。でも、誰かが抜けねば収まらないのなら…。
「いいよ、オラ一人でもできるから」
思わずそう言っていた。
一人になったことを報告すると、世話になったプロデューサーが言った。
「もう東京も大阪も出尽くした、あとは地方からやって来る」
かわいがってくれた先輩が言った。
「芸能界はティッシュと同じやで。次から次に出てくる、だからお前しかできないティッシュにならなあかん。芸能界というとこは、席がちゃんとあるんや。その人が辞めたらそこに次が入るようにできてるんや。だから十日市も、チャンスがきたとき座れるように、誰の席に座れるかを、自分でターゲット決めてやれ」
しかし、それはなんだろう。考える日々が始まった。
追いかけるより、追いかけられるほうに
トリオを脱退し、大手プロダクションも辞めて移籍。今度は、日本の3分の2のナレーターが所属する事務所である。声優の勉強など何ひとつしていなかったが、仕事は来る。30の坂を越えた十日市は、初めてのナレーションに挑んだ。
お笑いの世界とは違い、マイクひとつあるだけの殺風景な現場。机に紙が置いてある。これを読めばいいらしい。
「ステキにお仕事しましょう、ファッションカンパニーちくま」
「十日市さん『ちくま』が、『つくま』に聞こえるんですよ、もう1回お願いします」
「ちくま」
「イヤー、どうしても『つくま』ですね」

三つ子の魂百まで。どうしても八戸弁の発音になってしまう。延々1時間も収録は続いた。
「まだお笑いやってるほうがいい」と、当時を振り返って十日市は苦笑いする。
初仕事のギャラが振り込まれたのは3ヶ月後。額を見て驚いた。お笑いの仕事よりも、はるかに高額だったからだ。それからは、コマーシャルなどのナレーションを数多くこなした。ワイドショーのリポーターの仕事も舞い込んだ。13年待たせた幼なじみの恋人とも、晴れて結婚。すべてが順調に回っているかに思えたが、あるとき、リポートの現場で渦中の人物を追いながらふと考えた。
「オラは追いかけるんでなく、追いかけられるほうになりたかったんでないのか?」
プロデューサーや先輩の言葉が浮かんだ。八戸から来たオラの〝空いてる席〟は、どこだ―。そこからの行動は早かった。リポーターの契約が切れると同時に一切の仕事を断り、カメラ1台だけを携えて、青森県1周の旅に出た。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。





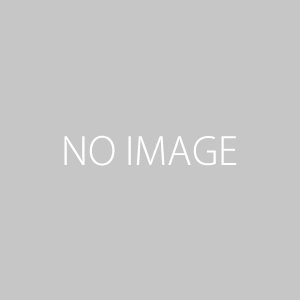
この記事へのコメントはありません。